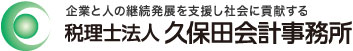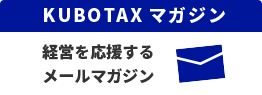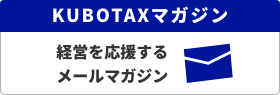KUBOTAX BLOG
- HOME
- KUBOTAX BLOG
- 相次相続控除について
相次相続控除について
2025年10月29日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相次相続控除についてお話させて頂きます。
【制度の概要(短期間の連続相続で使える特例相次相続控除とは?)】
相次相続控除とは、同じ財産に短い期間で二度相続税が課税される「二重課税」を防ぐための制度です。
具体的には、10年以内に2回以上の相続が発生した場合に、前の相続(1次相続)で
課税された相続税の一部を、今回の相続(2次相続)の相続税から差し引くことができます。
【適用を受けるための3つの条件】
相次相続控除を適用するには、次のすべての条件を満たす必要があります。
・相続人であること
今回の相続(2次相続)で財産を取得した人が、相続人であること。
(遺贈を受けた人などには適用されません。)
・10年以内の連続相続
今回の被相続人(亡くなった人)が、1次相続で相続人として財産を取得し、
かつ、1次相続から今回の相続までの期間が10年以内であること。
・1次相続で相続税が課税されている
今回の被相続人(亡くなった人)が、1次相続の際に実際に相続税を納付していること。
【税金への影響:控除額の決まり方】
この控除の金額は、前の相続(1次相続)で今回の被相続人が納めた相続税額を基に計算されます。
重要な点として、控除額は1次相続からの経過年数によって減少します。
期間が短いほど有利:
1次相続から今回の相続までの期間が短いほど、控除できる金額は大きくなります。
期間が長いと不利:
逆に期間が長くなるにつれて控除額は徐々に減少し、10年経過すると控除はなくなります。
つまり、1次相続からの期間が短いほど、控除額が最大となり、税負担の軽減効果も最も大きくなります。
【実際に適用する際の注意点】
・申告要件なし
この控除は、申告書を提出しないと受けられない、というものではありません。
この制度を利用して納税額が発生しない場合は申告は不要です。
(ただし場合によっては納税額が発生しない場合でも申告をした方がいい場合もありますので検討が必要です。)
・遺贈では使えない
適用を受けるための3つの条件にも記載しましたが、相続人でない場合は適用できません。
遺言による遺贈や死亡保険金の受け取りで財産を取得した場合でも、この制度は適用できません。
・1次相続の相続税申告が必要
この制度を適用するには、計算するための資料として前回の相続税申告書が必要になります。
相続税申告書を紛失している場合は、税務署で閲覧することは可能ですが、
非常に手間のかかる作業が必要になります。
申告書はきっちり保管しておきましょう。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。
お待ちしております。
(免責事項)
当サイトに記載した情報については、十分な検討・確認作業を行っておりますが、その情報の正確性・完全性についての保証をするものではございません。
平日 9:00 ~ 17:30